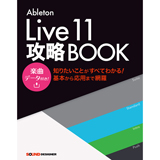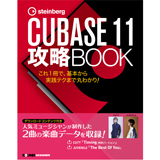前作『EXISTENCE』とは全く逆の、心を癒すカバー曲満載!
デーモン閣下『うただま』インタビュー
デーモン閣下『うただま』インタビュー
2017/11/24
3月に「らしさ」溢れる正統ハードロックアルバム『EXISTENCE』を発表し、全国ツアーを敢行したばかりのデーモン閣下。まだその余韻の残る中、前作とは全く逆の音楽的アプローチによる新作『うただま』がリリースされた。従前のデーモン閣下のイメージをくつがえす、優しく響く歌声とアンプラグドな楽器によるカバー曲の数々。ここでは、アルバムのコンセプトや収録曲の選曲理由など、本作の核心に迫るべく閣下を直撃。ファン必見のインタビューだ!
取材:布施雄一郎/東 徹夜
──前作『EXISTENCE』からわずか半年で新作をリリースするとは、とても驚きました。
デーモン閣下:それが狙いだからな。ワハハハハハ(笑)
──しかも、往年の名曲のカバーを中心としたアルバムとしたのは、どのようなきっかけからなのですか?
デーモン閣下:ポイントは2つあって、そもそもの話をすると、「1年に2枚のソロ・アルバムを出そう」というプロデューサーのアイデアがあった。1枚は、世の中的に認知されている「吾輩と言えばこういう音楽」というハードロックのアルバムを作る。そしてもう1枚は、いわゆるロックではない吾輩の音楽的側面をクローズアップしたアルバムをすぐに出そうと。だから最初から、『EXISTENCE』と2作品セットで考えていたということが、まずひとつ。ふたつめは、最初にプロデューサーが出してきた企画が、「優しいうた」だった。でも、静かな曲やバラードという概念ではなく、聴いた後に優しい気持ちになれることが大事だ、と。そこで彼が、「たとえばこんな曲」と10曲ほどを挙げてきたんだが、「こんな曲」と言うくらいだから、当然、既成の音楽なわけで。
──そこでカバー曲を中心とした作品という方向性が定まってきたんですね。
デーモン閣下:本格的に制作に入った段階で、その候補曲から6〜7曲ほどを選んで、残りの曲をどういう風に選ぼうかとなった時に、今度はアレンジの話になるわけだ。『EXISTENCE』はハードロックのアルバムだから、極端な話、こちらは、全曲ピアノと歌だけでもいいというくらい、歌を聴かせるアルバムにしよう、と。でも、たとえば井上陽水氏の「少年時代」は、以前にライヴでやったことがあって。その時に、尺八と十七絃箏、二十絃箏と一緒に歌うという、今回のアレンジとほぼ同じスタイルで演奏していて、その感じで入れたいと思ったのだ。だったら、他の曲も、最小限度の楽器編成で、かつ歌がちゃんと聴こえてくるんだけれども、聴き手に「へぇ!」と思ってもらえるような楽器選びをしていった、という流れだった。だから、やもすると、「面白い楽器と一緒にいろいろやってますね」といった視点で見られがちなんだけれども、そうなってはダメで、そこは、アレンジやミックスでも常に意識をしていた。要するに、「ここはプレイが面白いから、歌が引っ込んでしまっても、ここのプレイもっと聴かせようよ」となってしまうと、「いやいや、それは主旨からは外れるぞ」ということだ。
──そうしたコンセプトの元で、どのように選曲をしていったのですか?
デーモン閣下:一番大事なことは、歌いこなすことができるかどうか。吾輩の声質とかも含めてね。そこから先は、このアルバムのコンセプト、つまり「優しいうた」が、イコール「バラード」ではなく、賑やかな曲でも、聴いた後に、「優しい気持ちになれるうた」だというキーワードは、非常に重要なポイントだった。だから、実は10曲中、8曲がメジャーコード(長調)の曲なんだ。これは、吾輩のアルバムでは珍しいことで、聖飢魔IIも含めて、長年、マイナーコードの曲を歌い続けてきたから、それは大得意なんだな。ただ、明るい曲は苦手でな(笑)。結果的に、吾輩が作ったオリジナルの2曲だけがマイナーコード(短調)で、あとは全部メジャーコード。そういう意味では、吾輩にとっては、すごくチャレンジしたアルバムと言えるものになったな。
──その中でも、長調の「君が代」は最大級のチャレンジだと感じました。この曲へ込めた想いは?
デーモン閣下:元をただすと、「千秋楽」と「君が代」は、どちらも稲葉明徳(雅楽奏者)氏のアイデアから作り始めた曲なんだけれども、「君が代」に関して言うと、4〜5年前に、稲葉氏が「長年温めているアイデアがあって、一度聴いてもらえますか?」と持ってきてくれた。それが、従来の認識とはまったく違うコード進行で、背後でずっと篠笛が鳴っているという、極めて爽やかな、青空が広がるような長調の「君が代」で、まず、そういったアプローチがあるということに驚いて。ただ当時の吾輩には、この曲を入れられる作品が何もない状態で、「すぐには難しいが、機会が来たら」ということで、その時は終わっていた。
──今回その機会がやってきたわけですね。
デーモン閣下:『うただま』を作るにあたって、早い段階で「千秋楽」を入れたいと思っていて、残りの1、2曲をどうしようかと考えていた時に、急に稲葉氏の「君が代」を思い出してスタッフに聴かせたら、「こんな“君が代”は聴いたことがない!」と盛り上がって。「君が代」という音楽そのものが持っているポテンシャル、こういう風にアレンジすると、こんな風に聴こえるんだという、極めて音楽的な観点で「君が代」のよさを知ってしまった以上、これはやろう、と。いろんな歴史を背負っている曲だけれども、この曲の音楽的な才能を見つめてあげようよといった、そんな気持ちが強かったな。
──他にも、「見上げてごらん夜の星を」「故郷」など、名曲のアレンジや、要所に入る3つの「Interlude」、さらにはアルバムのパッケージデザインも含めて、とてもアート性の高い作品だと感じました。
デーモン閣下:そう言ってもらえると嬉しいんだが、ただその領域は、自分の中ではもう分からない部分で。「Interlude」に関しても、最後の最後、マスタリングの日まで「これ、要るかな?」と考えていた。でも、数学とは違って、“正解”のないところが、モノ作りの面白い部分でもあって。もっと踏み込んで言えば、この「Interlude」は、我輩のために入れたと言っていいだろうな。だからこそ、「要るかな?」と考えてしまうわけだ。「自己満足的なものになってないだろうか?」「蛇足ではないだろうか?」と。だけど吾輩は「入れたい」と思ったわけで。こうしたエゴとの闘いが、アートとエンタテインメントの境目なのかもしれないな。
──閣下は、その“境目”を、どのように見定めているのですか?
デーモン閣下:時間を空けて客観的に聴ければ、すごく分かりやすいだろうな。でも哀しいかな、制作にそんなに時間を空けられることってあり得ないわけで。制作中に、入院でもしない限りな(笑)。だから吾輩はどう工夫しているかと言うと、スタッフの顔色を伺うわけだ(笑)。
──ただそこは、一人宅録で音楽を作っている人にとっては大きな悩みでしょうね。
デーモン閣下:自宅で一人、自分のやりたいことだけをコツコツと突き進む面白さや快感は、すごくよく分かる。だけれども、そういう人が、「これでいいのかな?」と悩んでいるのであれば、その理由は、簡単に言えば「自分はいいと思うんだけど、他の人はどう思うんだろう?」ってことだろ? 自分だけで成立していれば、何も悩む必要はない。ということはだ、自分が作った曲を誰かに聴いてもらわない限り、その悩みは解決しないのだから、意見を受け入れるかどうかはさておき、悩んでいるのなら、人の感想を聞くということは“アリ”だろうな。でも、それが嫌いだから“おひとり様”なわけで(笑)
──確かに、おっしゃる通り(笑)
デーモン閣下:「うるせぇーよ。そんなこと、こっちは分かって作ってんだよ!」って、だいたいは聞く耳を持たない(笑)。だから、そういう人へのアドバイスって、本当に難しいんだけれども、全然知らない人と出会ったり、交わることの面白さに一度気が付くと、いろんなことがバーッと広がると、吾輩は考えている。今回も、初めて一緒にやったプレイヤーも何人かいて、そうするとだな、プロでこれだけ長く音楽を作ってきた吾輩でも、「へーっ!」と思うことが、いまだにたくさん出てくるわけだ。
──具体的には、どういうことが?
デーモン閣下:たとえば、クロマティック・アコーディオン奏者の小春(チャラン・ポ・ランタン)嬢。もちろん、アコーディオンっていう楽器は昔から知っているし、coba氏と一緒のステージに立ったこともあるけれど、スタジオでアコーディオンの音を本気で録ったのは、今回が初めてだった。するとだな、「想像以上に音圧があるんだな」とか、「右側と左側とで、出てくる音がこんなに違うのか」ということに気付くわけ。そうすると、「プレイヤー本人は、どんなバランスで、どういう風に聴こえるのが“一番いい音”だと思うのか?」と、いろんな疑問が出てくるし、それを本人に質問すると、意外な答えが返ってきたりして。そうした興味深さは、一人で音楽を作っていては体験できないことだからね。今回は、二胡やリュートの録音でも、そういった新しい体験ができたな。
──メジャーコードの楽曲をたくさん歌ったり、斬新なアレンジを取り入れたりと、閣下にとって、新しいチャレンジが多い作品だったのですね。
デーモン閣下:きっとそうすることが、吾輩は好きなんだな。そもそも、「歌とピアノだけで」という話から始まって、こんな複雑なチャレンジまでは求められていなかったのに(笑)。でもそれはやっぱり、「この時はああでさ」「あの曲はこうやって」っていう、こういうインタヴューでの土産話も、曲を作りながら一緒に獲得していきたいという気持ちが、きっと吾輩の底辺にあるからなんだろうな。それは、「ありきたりなことはやりたくない」と言い換えることもできて、結果、演奏している人も面白い、使ってる楽器も面白い、アレンジも面白い、ジャケット周りも面白い、ミュージックヴィデオも面白い作品にできたと思っている。「別に、どれかひとつくらい、面白くなくてもいいんじゃない?」っていうところには留まらない。吾輩がモノ作りをする時には。
この記事の画像一覧
(全0枚) 大きなサイズで見る。
関連する記事
2018/07/02
2017/10/05
2017/03/27
2017/03/17
2017/01/18
ニュース
2023/12/25
2023/12/20
2023/12/18
インタビュー
2023/03/23
2022/09/15
2022/05/26
2022/01/26
特集/レビュー
2023/04/03
レクチャー
2022/11/15
2022/11/01