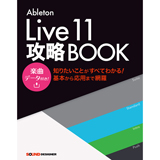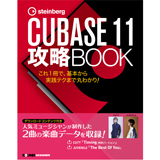ジャズ・ヴォーカル&ピアノの女王
ダイアナ・クラール、3年振りとなるジャパン・ツアーが東京からスタート!(11月5日(火) Bunkamuraオーチャードホール)
ダイアナ・クラール、3年振りとなるジャパン・ツアーが東京からスタート!(11月5日(火) Bunkamuraオーチャードホール)
2019/11/06
 ダイアナ・クラール
ダイアナ・クラール写真:土居政則


昨日からジャズ・ヴォーカル&ピアノの女王「ダイアナ・クラール」の3年振りとなるジャパン・ツアーが東京からスタートした。その初日公演のレポートと写真をいち早くお届けしよう!
ジャズってこんなに優美で、抒情的で、心をうるおしてくれるものなのか。ダイアナ・クラールの歌やピアノを聴くごとに、ぼくはまろやかな気分に満たされる。低く芳醇で伸びやかな歌声、粒立ちの良いピアノ・タッチとメロディアスなフレーズ、メロディを崩し気味に歌う時の得も言われぬブルース的な感覚・・・・・「ああ、彼女はナット・キング・コールやオスカー・ピーターソンの音楽が大好きなんだろうな。そして美しい旋律をこよなく愛し、それを自らの語り口でリスナーに伝えることを至上としているのだろうな」と思わずにはいられない。自分が初めてダイアナの音楽に触れたのは今から四半世紀以上前、ジャズ雑誌の編集をしていた頃までさかのぼる。とあるレコード・ディーラーが、カナダのインディペンデント・レーベル“ジャスティン・タイム”が制作したアルバム『Stepping Out』を輸入販売に先がけて聴かせてくれたのだ。「なんのてらいもなく、ひたすらノーブルにスウィングする若手が現れたな」と、爽快な気分にさせられた。もっとも、その後グラミー賞の常連となり、世界の大会場でソールド・アウト続出の公演を行ない、ジャズ界のファースト・レディ的存在になろうとまでは予想できなかったが。
1990年代半ばにメジャー・デビューを果たし、プロデューサーのトミー・リピューマ、ストリングス・アレンジの魔術師というべきクラウス・オガーマン(もうふたりとも亡くなってしまった)と出会い、ダイアナの音楽は洗練の度を強める。ボサノヴァ、ポップス、ロックなどの名曲を次々とワン&オンリーの色に染め、一作ごとにマーケットを拡大していく。あの特徴的な歌声と贅を尽くした伴奏の組み合わせで、いろんな旋律を聴いてみたいという思いは誰もが同じということか。そのぶんスウィング感たっぷりのピアノ・プレイをディスクで味わう機会が少なくなってきたことは否めないが、ライヴ・ステージにおけるダイアナは嬉しいほどに“ジャズの虫”のままだ。大いに歌い、バンド・メンバーとアイコンタクトを交えつつピアノでアドリブを重ね、楽しげにグルーヴし、しかもしっかり品格を漂わせている。3年ぶりの来日公演の初日となる11月5日、Bunkamuraオーチャードホールでのステージは、まさにジャズへの愛、コンボ(小編成バンド)への熱い思いに満ち満ちたもの。しかも今回は、前回と違ってフィドル奏者もキーボード奏者も参加していない。ダイアナを含めて計4名というエッセンシャルな構成で、とっくりとアコースティック・ジャズのど真ん中を届けてくれるのだ。共演メンバーは3年前の公演にも同行したカリーム・リギンス(ドラムス)とアンソニー・ウィルソン(ギター)、さらに2008年頃のメンバーで久々の復帰となるロバート・ハースト(ベース)。彼は30数年のキャリアを持つベテランで、ウィントン・マルサリス(97年、ジャズ音楽家として初めてピュリッツァー賞を受賞)やその兄ブランフォード・マルサリスとの共演でも名声を博した名手中の名手だ。2010年にはロバート・グラスパーやクリス・デイヴを迎えて『Unrehurst, Vol. 2』というリーダー作品も残している。剛柔あわせもつロバートのベースを得て、ダイアナのユニットはさらに豊かな響きを得たと断言したい。
楽器を囲むように、大2台、小4台のスタンドランプが少々高めの位置で設置されている。ランプの色は暖かな電球色。時おり会場上部の照明がそこにアクセントを加える程度の、シンプルに徹したライティングがまた、音楽の良き薬味となる。イントロはピアノとギターのユニゾン、間もなく弾く手を休めたダイアナが客席に体を向けて歌い出したのは「ディード・アイ・ドゥ」。ナット・キング・コールに捧げた96年のアルバム『オール・フォー・ユー』に収録され、2016年の来日でも(少なくとも東京公演においては)オープニングで歌われていたナンバーだ。激しく恋に落ちたときの心境を、何度も何度も韻を踏みつつシンプルな言葉で表現した詞を、ダイアナは滑らかに歌いきる。彼女は自分の歌の間、ほとんどピアノを弾かない。そのかわりギターのアンソニー・ウィルソンが粋な和音を入れて、パフォーマンスに膨らみを加える。そして自分のソロ・パートになると、ヴォーカル・マイクを少し向こうに移動し、俄然、指を鍵盤に踊らせる。シングル・トーン(単音)とオクターヴ奏法をバランスよく織り交ぜながらのプレイに、いつかきいた「母国カナダで駆け出しの頃はピアノ専業のミュージシャンであった」という話を思い出す。64小節ほどの即興パートを経て、追いやっていたヴォーカル・マイクを手繰り寄せ、再び歌へ。磨き上げられた演唱に、オーディエンスは惜しみない拍手を送る。
フランク・シナトラの歌唱で広まった「オール・オア・ナッシング・アット・オール」の後は、再びコールゆかりの曲「L-O-V-E」へ。ダイアナは2017年のアルバム『ターン・アップ・ザ・クワイエット』収録ヴァージョン同様、イントロでまずストライド奏法を用いたピアノ演奏を聴かせ、ゆったりしたテンポでさまざまな愛の形を表現する。アンソニーもオクターヴ・ユニゾンも交えながら、小気味よいソロを繰り広げてゆく。彼の父は20世紀アメリカ西海岸ジャズの代表的ビッグ・バンド・リーダー/アレンジャーのジェラルド・ウィルソン。1930年代から約70年のあいだ第一線に立ち、まだ知る人ぞ知る存在だった頃のエリック・ドルフィー、ロイ・エアーズ、カマシ・ワシントンなどをいち早く後押しした偉人だ。どこかオーケストラ的な広がりを持つアンソニーのギター・プレイは、続く「ユー・コール・ジス・マドネス」でも存分に生かされていた。シナトラが古典的名唱を残した「アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン」は斬新なハーモニー+ボサノヴァ調のリズムで再生され、この夜一番のアップ・テンポだったであろう「デヴィル・メイ・ケア」ではカリーム・リギンスのドラムスが際立った技の冴えを示す。尋常ではないビートの推進力、メリハリに富んだ打撃。コモン、J・ディラ、ポール・マッカートニー、オスカー・ピーターソン、そしてダイアナと共演し、等しく刮目すべき成果を残しているミュージシャンなど彼のほかに誰がいるだろうか。
「クライ・ミー・ア・リヴァー」といえば、20世紀の音楽史上ではジュリー・ロンドンとバーニー・ケッセルの共演テイクが名演とされている。しかしダイアナとアンソニーの絡みはその今世紀版を提示する。「あなたも私のために、川のように多量の涙を流せばいいのよ。私があなたを思い浮かべてそうしたようにね」。ジュリーの湿り気あるハスキー・ヴォイスに対し、ダイアナは毅然と、どこかカラッとしている。続く「イースト・オブ・ザ・サン」は、いまのところダイアナ唯一のライヴ・アルバムである『ライヴ・イン・パリ』(2002年)にも収められていた一曲。心持ちテンポをあげ、短いスキャットも交えながら快唱するダイアナを味わうことができた。
拍手を終え、静まり返った客席にダイアナは「もうすぐジョニ・ミッチェルの誕生日ね」(11月7日)と語りかける。そしてジョニが元気であること、彼女からいかに影響を受けてきたか、尊敬しているかを伝え、1971年リリースの金字塔『ブルー』に入っていた「ア・ケイス・オブ・ユー」をダイアナならではのセンスで再解釈。しかも途中のピアノによるパートでは、レナード・コーエンの「ハレルヤ」の一節も飛び出した。『ブルー』の頃、ジョニとレナードが恋仲だったという説を踏まえての引用なのか果たして、答えはダイアナのみぞ知るといっただろうか。さらに2006年のアルバム『フロム・ディス・モーメント・オン』から「アイ・ワズ・ドゥーイング・オール・ライト」、2009年リリースの映像作品『ライヴ・イン・リオ』から「チーク・トゥ・チーク」と、スタンダード・ナンバーを連発してライヴ本編は締めくくられた。無人のステージにはまだ奏でられていない楽器が残っているというのに。
アンコール1曲目は、大昔に「夢破れし並木道」という邦題がつけられていたこともある「ブールヴァード・オブ・ブロークン・ドリームス」。ここで初めてアンソニーがアコースティック・ギターを手にした。カリームはマレットを用いた丸く太いサウンドでリズムを装飾する。そして本当のオーラスは、「ザ・ルック・オブ・ラヴ」。全米だけで160万枚を売り上げ、一躍ダイアナの名をジャズ外にも轟かせたアルバムのタイトル・チューンだ。もちろんバート・バカラックが書き、セルジオ・メンデス&ブラジル‘66等が流行らせた往年の名曲なのだが、その換骨奪胎ぶりは、曲名の前に“ダイアナ・クラールの~”と太字で特筆したくなるほど。柔らかなストリングスが入っていたアルバム・ヴァージョンよりも一層タイトに親密に、ジャズのコクをたっぷり感じさせながらのパフォーマンス、そのなんと小気味よいことか。
見事な曲順、構成で楽しませてくれた初日のステージだったが、ジャズの世界ではよくあることとして、セットリストは事前に用意されておらず、そのときのダイアナの乗り、気分でレパートリーが決まったのだという。本日、そして明日以降の公演ではいったいどんな曲が唯一無二の歌声とピアノ・タッチで表現されるのか。加えて子供たちと一緒に初めて日本に来れたこともあるのか、今回のダイアナはとにかく快活だ。ジャズへの愛、音楽への愛に満ちたパフォーマンスは、どの日どの会場に足を運んだファンにも歓びをもたらすに違いない。
レポート「原田和典」
関連する記事
ニュース
2023/12/25
2023/12/20
2023/12/18
インタビュー
2023/03/23
2022/09/15
2022/05/26
2022/01/26
特集/レビュー
2023/04/03
レクチャー
2022/11/15
2022/11/01