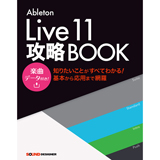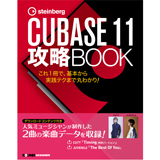35周年を記念したデビューアルバムのリテイク&リミックスアルバム
角松敏生『SEA BREEZE 2016』インタビュー
角松敏生『SEA BREEZE 2016』インタビュー
2016/03/15
『SEA BREEZE』をやり直せるということは、スゴく刺激的な作業になりましたね。
角松:今年、デビュー35周年ということで、何かやれないかと色々考えていたんです。たまたま権利関係を調べていたら初期の作品のマスターが使えることがわかりまして、それでソニーに確認をしてもらい、大急ぎで倉庫からアナログマルチテープを持ってきてもらったんですよ。ただアナログテープというのは磁気を糊で固めているんですね。この糊が経年劣化で剥がれてきてしまうので、粉がポロポロ落ちてきて、昔カセットテープが回らなくなったりしたじゃないですか。あれと同じ状態になるわけですよ。なので、これを現在の技術でトースティングと言うんですが、熱処理をして高温で焼くんです。それで一瞬固めたものが一回か二回、回るんですよ。その間にデジタルにA/D変換しました。
──失敗したら二度と使えないのですか?
角松:はい、これは一発勝負です。幸い管理されている状態が良かったので成功しました。以前、別の企画で83年のライブのアナログ音源があったんですけど、それは回りませんでした。多分テープのメーカーにもよると思うんですが、再生は一曲だけしかできませんでした。その轍があったので、どうかなとは思っていたんですが、なんと全曲アーカイブができたと聞かされて。“じゃあこれは面白いことができるんじゃないか”と。で、オケはそのままに、歌を録り直しました。
──以前はセルフカバーのアルバムを出されていますよね。それとの違いは?
角松:今から5年ほど前にリメイクアルバム『REBIRTH 1〜re-make best〜』というのを出していまして。その作品は完全に全部録り直しで別解釈のものなんです。今の力量があったら“こんな風にしているだろうな”という作品です。それはそれでファンの間でも評判が良かったですね。その当時のままのオケでアルバムを丸ごと1枚作るというのは、皆さんあんまりやられていないんですよ。ただ、やはり自分がプロのシンガーとして過去の自分を批評した時に、本当は歌い手としてデビューしちゃいけないような人だったんですよ。
──当時聴いていた時はサウンド全体のクオリティが高かったのであまり感じませんでした。
角松:おそらく、ソングライターとして声の質とかそういうものに対しては当時のメーカーの人は面白いと言っていたんでしょうけど。僕は歌謡曲のセクションからリリースしたんですよ。そのいわゆるアイドル路線のようなセクションからデビューしたものですから。まぁ僕もよくわかっていなかったし。歌なんか上手くなくてもいっちゃえばいいんじゃんみたいな、割とわかりやすく言えばそんなような雰囲気だったと思います。自分でプロデュースできるようになってから、その当時のことを俯瞰すると、やっぱり “僕の作品だけど僕の作品にできてない” という未練が最初の2枚にはあったんです。なので、これをやり直せるということは、スゴく刺激的な作業になりましたね。
──しかし当時、デビューアルバムであれだけの大物スタジオミュージシャンがバックに付いたということは業界的に “スゴいヤツが出てきた” という感じだったのではないのですか?
角松:違いますよ、当時はお金があったんですよ。歌謡セクションですから、いわゆる西城秀樹さんとか近藤真彦さんとか、そういうところで潤っていましたから。それで、面白そうだからということで。極端な言い方をすれば、やってみようぜみたいな感じですよね。一流のスタジオミュージシャンは歌謡界でも活動していましたから。ですから “ドラムはポンタ(村上秀一)で、後藤次利にアレンジしてもらってさ” みたいなそういう話し合いが僕の知らなかったところでどんどん進行していたんですね。まぁ、とはいえ今となっては良い経験だったと思いますよ。よく分からないなりに様々な知識を吸収できましたしね。
──本作では、ボーカルトラックをリテイクされたわけですが、35年経って当時と現在で発声や歌いまわしなど、ボーカルスタイルで一番変わった部分はどこですか?
角松:単純に体ですよ。2つ目の事務所に移籍して、そこが良かったのはライブをコツコツやってお客さんとの絆を深めていこうという方針だったんです。移籍先の社長はライブに対する思い入れが強い方だったので、たくさんライブをやらせてもらいました。だからそれが僕にとって良かったんです。レコードだけでなく、生の角松敏生のパフォーマンスや人間としてのパイブレーションによって、お客さんが増えていったということが大きいですね。結局、ライブをやり続けていくうちに何かを掴んだんです。
──では、ここから変わったという具体的な意識はなかったのですか?
角松:僕が日本レコード大賞アルバム賞を受賞した6枚目のアルバム『TOUCH AND GO』というのがあるのですが、その辺りまではダメでした。ダメというのもおかしいのですが、3枚目以降の作品は僕自身がプロデュースをできることになり、好きなようにやらせてもらっていたんです。そこで、自分の歌に対するコンプレックスを解消するにはどうすれば良いのか考えた時にダブルボイス(同じ人が同じメロディーを重ねて録音し声に厚みを加える)を採用したんです。それで、ようやくレコーディングに関しては自分の中で”嫌さ加減”が軽減したんです。その時代が『TOUCH AND GO』まで続くんです。でも、ライブで歌を歌ったり、自分で歌をディレクションしていくうちに以前の作品よりも納得いくものができはじめたんです。
──それは主にどの部分なのでしょうか?
角松:これは主に音程感なんですけど、僕はスゴい音程ノイローゼの部分があって、音程に対して厳しすぎると周りから言われるんですよ。スタジオで自分がディレクションして何度もやり直したりする試行錯誤が自分にとって良い勉強になりました。その次のアルバム『BEFORE THE DAYLIGHT』を作る時に、海外の方にプロデュースしてもらうことを考えたんです。それまで全部自分でやってきたんだけれども、“NYやLAの旬なプロデューサーがやったらどうなるだろう?” と。すると、曲に関しては、向こうが “あれやろう、この曲をやろう” って食いついてくれたんです。ただ海外のプロデューサーが手掛ける時は、歌も向こうの意向に沿ってやらなければいけなくて。彼らは日本語がわからないわけじゃないですか。言葉云々ではなく、歌ってそれでOKを出すというだけなので、 “ダブルボイスでやりたい” なんて言えないわけで、覚悟を決めてレコーディングしましたね。
この記事の画像一覧
(全0枚) 大きなサイズで見る。
関連する記事
2022/05/15
2022/03/25
[div class="link">角松敏生、『MILAD #1』 4月13日(水)先行配信決定!2017/06/09