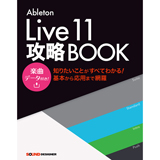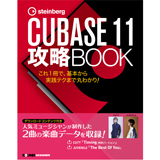35周年を記念したデビューアルバムのリテイク&リミックスアルバム
角松敏生『SEA BREEZE 2016』インタビュー
角松敏生『SEA BREEZE 2016』インタビュー
2016/03/15
角松:意外にいけたんです。以前、2枚目のアルバムをロサンゼルスで録った時は、エンジニアに “英語の発音が悪い”と言われたり、シンガーとしては全然ダメだと思われている空気になっていたことをよく覚えています。しかし、それから6〜7年経ってNYでやった時はプロデューサーが割と普通に作業してくれまして。それでちょっと自信がついたんです。その次の『REASONS FOR THOUSAND LOVERS』では海外プロデューサーと自分が手掛けたものをミックスしたのですが、徐々にダブルボイスをやめていましたしね。さらに、オリジナルとしては11枚目になる『ALL IS VANITY』の時には歌の複雑なハーモナイジングだとかやり始めたんです。過去の経験を糧にバックコーラスも自分でやるなどチャレンジもしました。あとは海外のコーラスの人たちをどうやってコントロールするか。そのボーカルプロダクションに関して、やってみようって思ったのが『ALL IS VANITY』でした。今思えばやり直したいところもあるんですけど、あの作品に関してはもう自分自身では歌の扉が開いた作品だと位置付けています。“僕は歌手です” とようやく言えるようになったのが10年目ですよ。
──たしかに当時『ALL IS VANITY』はご自身のベストだといろいろなメディアでおっしゃっていましたよね。
角松:『ALL IS VANITY』を担当したのが、ウンベルト・ガティーカというグラミーを受賞したエンジニアでした。彼はTOTOなども手掛けていて。正直、とっつきにくいというか少し変なおじさんで、最初は小馬鹿にしているような感じでした。でも、ミックスの時に聴きに行ったら “おい、これはお前が歌ってるのか?” って聞かれて “イエス” って答えたら、“ You good singer! ”って言ってくれて。もうそれはとても嬉しかったです。そこから歌の分量が増えていって、コーラスワークとかも楽しくなりました。ただ、すぐ凍結で辞めちゃうんですけど(笑)。
──凍結中(活動停止中)もプロデュースした作品でコーラスワークをたくさんされていましたよね?
角松:凍結するって決めた時に2枚組のベスト盤『1981-1987』を出していますが、その中にリメイクをたくさん入れているんです。本作収録曲である「YOKOHAMA Twilight Time」もその時実は一回やっています。そのベスト盤を今でも聴くんですけど、歌うことが楽しくて仕方ないというのがひしひしと伝わってきます。つまり、ちょうど10年経つまで試行錯誤を繰り返していたのが、現場を積み重ねているうちに自然に会得したということなんです。
──では、現在のボーカルスタイルになったのはやはり凍結期間中なのですか?
角松:その頃、色々なアーティストのプロデュースをやらせてもらい、コーラスもバシバシ入れてました。女性シンガーの楽曲を手掛けた時には、歌のニュアンスとかメロディラインのことを伝えるために仮歌も全部自分で2キー(男テイクと女テイク)作っていました。それで僕が歌ったものを聴いてもらって歌ってもらうという方法をよくやっていましたね。なので、実は「角松バージョン」の楽曲というものが存在するんです。それはavexさんに聞けばあるかもしれないですね。
──楽曲の仮歌を歌うことがポイントだったんですね。
角松:えぇ、僕の歌ったものが外に出ないということはわかっていたから、なんか楽しいわけですね。例えるなら、打ちっ放しのゴルフをやっているような気分で(笑)。そこがまた、知らず知らずのうちに稽古になっていたわけです。もちろん凍結している時なので、「角松敏生」という看板は背負っていないわけで、歌を歌うことに重点を置いて楽しんでいたんです。そういったものの集積が「WAになっておどろう」だったり、解凍宣言後に出したアルバム『TIME TUNNEL』に繋がっているわけです。そこから現在まで声の質やボーカルスタイルはブレていないですから。
いかにブラッシュアップするのかということを掲げて細かな作業をしました。
角松:今回は35年ぶりに内沼映二さんにやっていただきました。僕の多くの作品を一緒にやってますが、『SEA BREEZE』を実際に手掛けた方にやっていただいたわけです。これは記念すべきことなんです。ただ、内沼さんも面白かったのがオリジナルと色々イメージが違うんですよ。“何でこうしたの?” って聞いたら “いや〜なんか恥ずかしいからさ” って。エンジニアさんにもそういうことがあるんだなと。
──では今回直せるとういことで、内沼さんも喜ばれてまいしたか?
角松:喜ぶというよりも、僕が内沼さんに伝えたのは “最初の内沼さんのミックスで良いですよ” ってことです。リメイクするって決まった時、足したりだとかループをひいたりとかやってみようと思ったんですけど、やはり記念すべき作品ですから聴こえてくる音が、楽器の音一つ一つをとっても歌の一部になっているんです。例えばシュガーベイブ「SONGS -40th Anniversary Ultimate Edition-」を聴くと、当時の空気感を壊さないで忠実に再現されていました。でも、達郎さんもリミックス作品を出していますけど、意味合いが違うのは16chマルチってことなんです。
──当時はまだ24chのレコーダーがなかった時代ですよね。
角松:チャンネルがまとまっちゃっている場合ですよね。例えばドラムは1つになっていて、キックとスネアを別にできないんです。まぁ当然なんですけど。そうなると基本的に当時の空気感を壊さずにグレードアップさせるというやり方しかないですからね。けれど僕もミックスしていくうちに当時の空気感を損ねたくないなと思い始めまして。なぜならば、そうやって聴いてきたものだから。たとえば、“あれベースが聴こえない” って思ったらそれが歌の一部になってたんだなって、そこで気付くんですね。だからこのストラクチャーじゃなくて、オリジナルのようなミックスをして下さいって内沼さんに言い始めちゃったんです。基本的なディティールは当時のそのままに、なおかつ、それをどうブラッシュアップするのかということを掲げて細かな作業をしました。
──では今回は、新規で音をかぶせたりはしていないのですか?
角松:パーカッションやループをほんの少し足しています。ただ当時はシンクもクリックもない時代ですから合わせるのが大変だったんです。当時はドンカマチックという「カチカチ」と鳴るリズムボックスを聴きながら始まるんですけど、あとは聴いちゃいないんで、どんどんズレていくんです。だからクリック作るの大変でしたよ。一拍ずつテンポデータ打ち込んで行かないとクリックが作れないという。なんとかコンガやシェイカーを少し足すことはできました。
──DAWやってる人ならわかると思いますが、大変な作業ですよね。
角松:僕、ループは「Stylus」を使っているんですけど、あれはクリックが揺れたらそれに追従して揺れてくれるので、そういうソフトを使って強化をしたり。あるいは2曲目の「Elena」ではちょこっとピアノを入れてみて、知っているスタッフが聴いたら大笑いするだろうなといういたずらもしてみたり。あとはシンセに生のサンプリングの音を少しだけ重ねてみたりとか、生のキックに対してサンプリングのバスドラを少し足しています。これによって当時出せなかった低音のエッジや重みというのを表現しています。
この記事の画像一覧
(全0枚) 大きなサイズで見る。
関連する記事
2022/05/15
2022/03/25
[div class="link">角松敏生、『MILAD #1』 4月13日(水)先行配信決定!2017/06/09