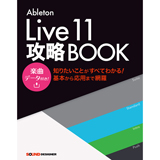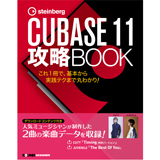打ち込みサウンドとビッグバンドのコラボレーション
角松敏生『Breath From The Season 2018~Tribute to Tokyo Ensemble Lab~』インタビュー
角松敏生『Breath From The Season 2018~Tribute to Tokyo Ensemble Lab~』インタビュー
2018/04/25
角松:あれすごいですよね? いままで娘がデジタル・ピアノを弾いてたんですよ。それが段々弾けるようになって曲が難しくなってくると、フォルテだメゾピアノだって出てくるといっちょまえに「弾きにくい」って言うわけですよ。うちの奥さんはピアノ弾ける人なので「そうだよね。違うもんね。」って話になって、じゃあピアノ買うかと。ただ僕の世代はピアノ買うってことが、どんだけ敷居の高いことかっていうトラウマがあるわけですよ。でも買うんだったら一生もんだよなってことで探し始めるんですけど、うちのスタジオブースはスペース的にアップライトしか置けないんですよね。そこで知り合いに「ちょっと娘のためにピアノ買おうと思ってるんだけど、スタインウェイのアップライトとかもあるんだよね?」って聞いたら、「アップライトはベヒシュタインですよ!」って言うわけですよ。ベヒシュタインって考えは僕の選択肢には無かったんだけど、僕もこだわりは強い方で、しかも疑り深いのでショールームに小林信吾さんに同行してもらって、「信吾ちゃんこれ全部弾いて!」っていって3時間ぐらいかけて4台くらいの個体を全部弾いて貰ったなかから選んだ1台なんです(笑)。
──贅沢ですね。
角松:その中の1台がこれなんですよ。それで届いて調律してレコーディングに使ったんですけど、最初はそんなに鳴ってなかったんですよ。これはちょっと外したかなって思ってたんですけど、だんだん鳴ってきて、マイク立てて録ったらとんでもねぇ良い音しやがったんですよ。「Morning After Lady」「Nica's Dream」がベヒシュタインですね。ミッドレンジがすごいしっかりしてるんですよ。太いものを細くすることは出来ても細いものを太くすることは出来ないっていうのが僕のこだわりなので。そしたら信吾ちゃんもやっぱりこれだなっていう感じでしたね。ベヒシュタインの話は是非書いてください(笑)
──映画「スウィング・ガールズ」以降、スウィングジャズやラテンにチャレンジする中高生の吹奏楽部が増えています。このような若い子達を応援する意味で、吹奏楽アレンジによるリメイクに興味ありますか?
角松:というよりも、僕の音楽を聴いていた世代の娘さん息子さんで吹奏楽をやってる方が意外と多いんですよ。だから実はそういう狙いがあるんですよ。「これ、お父さんカッコいいね!」って言われたいなと思って。だからここに挑戦しろ!ってことですよ。これが学校の課題になれば良いのにって思いますよね。
──吹奏楽の譜面出したら絶対売れそうですよね。
角松:だから逆に自分達で音を採りなさい! 自分で譜面起こしなさい! ってことですよ。例えば今は花形トランペット・プレイヤーとなっているエリック宮城君たちがまだ若いころに僕がプロデュースした『Breath From The Season』を聴いて憧れていたというお話を今回ご本人から聞きましてね。その世代が今この世界のトップクラスのプレイヤーなんですよ。その世代が当時「Nica's Dream」をブラバンでコピーしていたという話をよく聞きます。譜面なんかなくて。その話を聞いてるから今若い世代でブラス・アンサンブルやってる子たちにも是非聴いてもらいたいですね。お手本になるような楽曲がいっぱい入ってるので。ちょっと高度ではありますけど。
──今度のツアーは親子で観にくる方も多いんでしょうね。
角松:子供がブラスバンドをやってるんで、今回のアルバムは親子で楽しみにしてますっていう声もすごい多いです。やっぱり僕ら世代の40~50代っていうと中高生のお子さんお持ちの家が多いんですよ。だから逆に子供が中高生になったのでまたコンサートに行けますってのも多いですけど(笑)。
──今回ラテンやサルサなどのアレンジもありましたが、今後またそういう別アレンジでのリメイクを聴けるのでしょうか。
角松:例えば、ある程度の歳になってきたら、過去の曲を焼き直したりしながら顧客の皆様のみを対象に細々と演っていくっていうのが一番手堅いミュージシャンとしての生き方かとも思うんです。でも、やっぱり僕自身は制作者として新しいものを作ったりとか、次の作品に対してのモチベーションが無い訳ではないんです。ただそういうことをやっても、新譜はもうビジネスにならないんですよ。タイアップやアニメの主題歌で売れましたとかそういう複合的な理由があったら別でしょうけど。さらに質の高い曲、音が良いとか、そういう概念がビジネスにおいて常に必要とはされない時代です。当然僕のお客さんというのは、顧客として僕のブランド・イメージ、音の良さなども含め楽曲に対する確かさみたいなものに信頼を置いてくださっていると思っていて。だからそういう人たちに答えていくっていうのは今後も重要なことなので、ここ数年は過去の自分の思い残しっていう部分にスポットを当てて何作かやってきたんです。ただ実はもうここで、そろそろやめようかなというところがあって。
──完全新作ですか。
角松:単純にやりたい! やりたい! だけでは飯は食えないので、用意周到にやらなければいけないんですね。前作の『SEA IS A LADY 2017』もそうだし、今回の『Breath From The Season 2018』も1つの点なんです。布石って言ってもいいのかな。そこに向けて全部がこう線になっているみたいな。その線の到達点に向けて角松温度みたいなものを上げておくっていうことはすごい大事ですよね。ファンやその周辺の人たちに対してもう一回認知度を上げていくということ。その温度を持った人たちを引き連れながら自分のやりたいことへ導いて行きたいんですよ。『SEA IS A LADY 2017』にしろ『Breath From The Season 2018』にしろ、こういうものを作っておけば顧客の人には喜んでいただけるだろうというものをしばらくやって、角松ブランドに対する信頼を維持しつつ、次の新しいブランディング・イメージとしての自分のトライアルに向かっていきたいなと思いますね。
この記事の画像一覧
(全0枚) 大きなサイズで見る。