ユニバーサルオーディオ製のIFをプロが使う理由に迫る! 第七弾
UADプラグイン愛用ミュージシャンインタビュー【亀本寛貴(GLIM SPANKY)】
UADプラグイン愛用ミュージシャンインタビュー【亀本寛貴(GLIM SPANKY)】
2019/10/16
日本武道館、豊洲PITでのワンマンライブに続き、FUJI ROCKのメインステージでも異彩を放った男女2人組ロックユニットGLIM SPANKY。このGLIM SPANKYのギタリスト、亀本寛貴さんもUADプラグインの愛用者の1人だ。ここでは、11月20日にリリースされる新曲「ストーリーの先に」の制作エピソードも交えながら、日頃デモ作りで欠かせないという「UA 610-B Tube Preamp and EQ」や「Marshall Plexi Classic Amplifier」の使い方を聞いてみた。
取材:編集部 撮影:小貝和夫
──GLIM SPANKYでは、普段はどのように曲作りを行なうことが多いのですか?
亀本:僕がコード進行とかドラムのリズムパターンといった思いつくだけの伴奏を作って、それを松尾さんに渡してメロディーを付けてもらうか。逆に松尾さんが弾き語りしたメロディーや歌詞をもらって、それを後からアレンジする2つのパターンが主ですね。
──亀本さんはDAWソフトにLogic Proをお使いだとお聞きしましたが、伴奏やアレンジもそれを使って?
亀本:はい。デビューした2014年頃からそのスタイルです。
──現在、オーディオインターフェイスは何をお使いですか?
亀本:ユニバーサル・オーディオの「Apollo Twin」を2年くらい前から使っています。
──「Apollo Twin」をチョイスした理由というのは?
亀本:楽器屋さんに行ったときに、コンパクトなモデルの中でも割と高めな印象だったんですけど、僕としては長く使うことになるだろうと思ったし、それならばちゃんとしたものの方がいいかなと。あと、セイント・ヴィンセントさんがインスタグラムで移動用のエフェクターボードを紹介していたんですけど、その中にNative Instruments「Maschine」とか「Apollo Twin」が入っていて。「あ、こういうのを使ってパソコンで作業するんだな」って思って(笑)。
──「Apollo Twin」のセットアップは大変でしたか?
亀本:すんなりでしたね。UAD専用のミキサーソフトがある点は「あ、これを使うんだ」って思いましたけど、使い方とかはあんまり迷いませんでした。
──「Apollo Twin」を使用する前と後では制作のスタイルは変わりましたか?
亀本:そうですね。UADプラグインが使えるようになって、実機に近いからデモだからといって雰囲気が出ないというのが少なくなりましたね。あと、「Apollo Twin」はボリュームの調整もしやすいし、モニターとヘッドホンの切り替えもすぐにできるので、作業効率もすごく上がったことは間違いないと思います。
──では、実際に亀本さんがよく使用するUADプラグインについて教えてください。
亀本:まず「UA 610-B Tube Preamp and EQ」はよく使っています。ギター、ベース、鍵盤といった楽器をオーディオで録る場合は、これを必ず通しています。
──「UA 610-B Tube Preamp and EQ」を通すと音が変わりますか?
亀本:はい。これまでもギターの音を録ってパソコン上でアンプシミュレーターをかけたりしていたんですけど、同じギターの音でも「UA 610-B Tube Preamp and EQ」を通してアンプシミュレーターをかけると、だいぶ質感が変わってきます。僕の場合、普通のロックミュージシャンなんで、家でデモを作っている段階の音がすごく重要で、その音が生の質感に近寄るとやる気が出るというか、逆に言えば、近くないとなかなか入り込めないんですよね。そういった意味では、このプラグインがそういったことを解消させてくれたというか。
──「UA 610-B Tube Preamp and EQ」を使う際、パラメーターなどはどのようなセッティングにすることが多いですか?
亀本:「UA 610-B Tube Preamp and EQ」自体のパラメーターは特にイジってはいません。僕はギター、ベース、マイク、鍵盤といった楽器をハードウェアの小さなミキサーを経由させて「Apollo Twin」にルーティングしているんですが、音量などはミキサーで調整していて。なので、「UA 610-B Tube Preamp and EQ」は通すだけです。でも、通すだけで自分の好きな音になってくれます。
 ▲「UA 610-B Tube Preamp and EQ」
▲「UA 610-B Tube Preamp and EQ」
──では、ギターによく使うUADプラグインは?
亀本:ギターによく使うのは「Marshall Plexi Classic Amplifier」ですね。セッティングはこんな感じにすることが多いですね(下画面参照)。

 ▲「Marshall Plexi Classic Amplifier」
▲「Marshall Plexi Classic Amplifier」
──これは、どういった音になるのですか?
亀本:普通にレスポールの音がちゃんと歪む設定です。設定としてはスタンダードなものだと思いますね。僕はNative Instrumentsのアンプシミュレーターやファズとかでギターの音作りをすることもあるんですけど、これはちゃんとエレキギターのクランチとかを「バンッ」と入れなきゃならないときに使うものです。

──「Marshall Plexi Classic Amplifier」のアウトプットはリンクされているんですね?
亀本:そうですね。実機でもやるんですけど、リンクさせてますね。アウトプットとして「I」と「II」があって、「I」はわりとカリッカリなサウンドで、「II」はモコモコなサウンドなんですね。で、それを混ぜて使うみたいな。
──このセッティング以外だと、どのようにすることがありますか。
亀本:これ以外だと、よりボリュームを下げてクリーンな状態にして、少しクランチ気味にしてファズペダルを入れたり。
──そういった際には、EQとかコンプなども使うのですか?
亀本:音色によりますかね。例えば、すごくクリーンよりにした場合は、コンプを強めにかけてパコパコにすることもありますし。
──11月20日にリリースされる新作「ストーリーの先に」では、かなりエフェクティブなギターの音が聴けますが、デモ作りの段階ではどのようなプラグインを使ったのですか?
亀本:たしか、デモの段階ではLogic Proの「Pedalboard」に入っているエフェクトを使いました。一般的なエフェクター用のと違って、この「Pedalboard」に入っているギター用のペダルエフェクトはパラメーターが少ないし、デモの段階でポンポンと作っていくにはちょうどいいんですよね。何というか、ラフ画みたいなものがすぐに描けます。
──デモ作りではベースはどのようにすることが多いのですか?
亀本:最近はUADプラグインの「AMPEG SVTVR CLASSIC」を使うことも多いですね。この「ストーリーの先に」では、デモの段階ではシンベの音も混ぜて使ったんですけど、「AMPEG SVTVR CLASSIC」の「ultra-lo」をオンにすると結構低域が「ボンッ」と出るし。ベース用のシミュレーターでは一番似ているような気がします。

▲「AMPEG SVTVR CLASSIC」
亀本:この曲はドラマ『Re:フォロワー』の主題歌になることは決まっていたので、日頃からシャワーを浴びたり、ビールを飲んだりしているときに、なんとなくその雰囲気にあったものを探していて。で、いざ具体的に作ろうとなったときは、まず最初に楽曲の中心になる8小節くらいのコード進行から考えていきましたね。で、それをアコギで鳴らしてみて。そこから「どういうドラムサウンドにしようかな?」と進めていきました。僕はデモ段階で、ドラムのサウンドに関してはかなり重要視しているんですよ。
──実際にデモでは、ドラムはどんな感じに作られたのですか?
亀本:サンプルを2枚〜3枚くらい貼ったりして。とにかく、最終的に自分が「こうだな!」って思えるようなドラムのサウンドになるようにですね。
──その後は?
亀本:コード進行とドラムができたら、イントロの流れみたいなものを考えて。そこから「メインのテーマをどう入れよう?」っていう感じで、ワンコーラス分を作っていきました。
──松尾さんには、このタイミングでデモを渡すのですか?
亀本:そうですね。メロディーはない状態なんですけど、「Aメロこんな感じで、サビはこんな感じなんだけど」っていうのを渡します。で、例えば「AメロとかBメロのコード進行がやりづらい」みたいのがあればやり直しますし、メロディーが乗れば、そのまま使うという感じです。
──今回の「ストーリーの先に」の聴きどころは、亀本さん的にはどこになりますか?
亀本:どこだろう。ただ、今のGLIM SPANKYのテーマとしては「遅いBPMでもバシッと聴かせる」というのはあります。それは、歌のメロディーだけではなくて、間奏のギターとかもそうですし、インパクトのある覚えやすい、クオリティの高いものにしたいなと思っていて。僕らは2人でやってて、わざわざギタリストがいるんで。特にそういったところは大事かなと思っていますし、こだわって作っています。あと、最近の曲はみんな縦線にジャストなものが多いなと思っていて、あんまり後ろに引っ張らないものが多いと思うんです。なので、できるだけそういったところに挑戦したいという感覚も、今回の盤には込めてやっていますね。
──わかりました。ところで、UADプラグインに関して、今後使ってみたい製品などはありますか?
亀本:「AMPEX ATR-102」にとても興味があります。あのクルクル回っているテープの絵がいいですよね。この製品は使っている人が多いなというイメージもあって。
──今日はこちらのフックアップさんのスタジオで「AMPEX ATR-102」が試せるそうですよ。
亀本:それはすごく楽しみですね。(※亀本さん、自身のギターを抱えて「AMPEX ATR-102」を通した音をあれこれと試してみる。その後、さらに興味の出た「Neve 1073」「Galaxy Tape Echo」「Fender '55 Tweed Deluxe」も試奏する)
 ▲「AMPEX ATR-102」
▲「AMPEX ATR-102」
──どうでしたか? 実際に「AMPEX ATR-102」を通した音は?
亀本:全然違いますね。ちょっとジミ・ヘンっぽい音になるというか。60〜70年代っぽいギターの音になります。すごくいいですね! 僕らはロックミュージックで、特にオールドな質感のものなので、パソコンだけだとやっぱ雰囲気が出ないなってときもあるんですけど、そういうのに一役買ってくれるものだなと思います。
──GLIM SPANKYのレコーディングもテープを使うことはあるのですか?
亀本:以前、ドラムのレコーディングに使ったこともあったんですけど、今は使うことはあまりないですね。僕はかなり好きだったんですけど。
──この「AMPEX ATR-102」ならばドラムにも使えそうですか?
亀本:そうですね。今、「リバーブを深めにかけたドラムにかけたら良さそうだな」って思いました。先ほども話した通り、僕はデモ段階でのドラムの音がかなり重要だと思っているので、こういうプラグインはぜひとも活用したいですね。あと、「Neve 1073」も「Galaxy Tape Echo」、「Fender '55 Tweed Deluxe」もかなりいいですね。知り合いのギタリストも結構「Fender '55 Tweed Deluxe」を使っているんですけど、マイキングとかも変えられるし。音もいい感じだと思いました。

▲「Neve 1073」

▲「Fender '55 Tweed Deluxe」
 ▲「Galaxy Tape Echo」
▲「Galaxy Tape Echo」
──では、最後にあらためて、ユニバーサル・オーディオ製品やUADプラグインはどのような人にオススメだと思いますか?
亀本:とにかく生楽器とかマイクを使った曲作りをするのにオススメだと思います。ソフト音源とかが中心の人だったら別の選択肢もあると思うんですけど、生の楽器を録るにはこれしかないんじゃないかなと思いますね。
──それは「Unison」機能でかけ録りができるという点も大きいですかね。
亀本:はい。かけ録りできるところももちろんいいですし、普段生演奏の環境にいる人には「出音」が一番しっくりくるんじゃないかなと思います。アナログの感じをうまく、違和感なく再現してくれているというか、これはもう「すげぇ!」って感じですね。
関連する記事
2019/09/24
2019/09/05
2019/08/30
2019/08/22
2019/08/09
ニュース
2023/12/25
2023/12/20
2023/12/18
インタビュー
2023/03/23
2022/09/15
2022/05/26
2022/01/26
特集/レビュー
2023/04/03
レクチャー
2022/11/15
2022/11/01




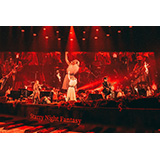



















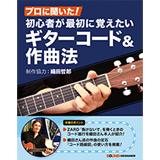
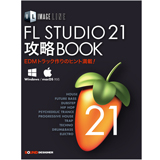
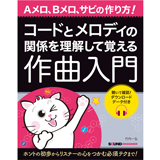

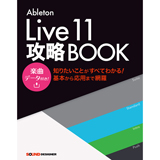
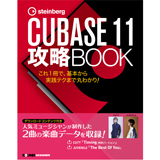


 製品名: Arrow
製品名: Arrow 製品名: Apollo X6
製品名: Apollo X6 製品名: Apollo X8
製品名: Apollo X8 製品名: Apollo X8P
製品名: Apollo X8P 製品名: Apollo X16
製品名: Apollo X16

